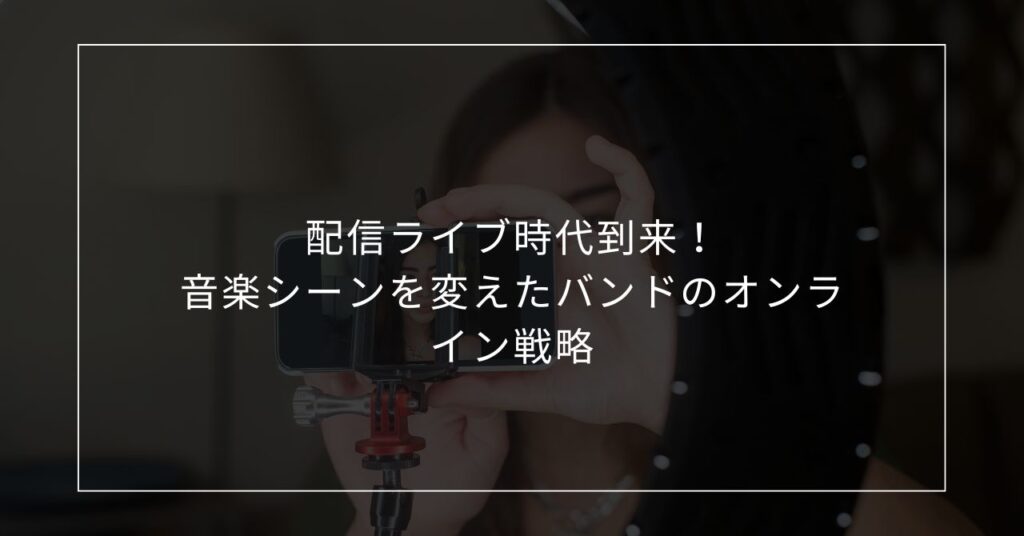
2025.04.04
コロナ禍以降、ライブの形が大きく変化した音楽業界。かつては“会場に足を運んでこそ”だったライブ体験が、いまやインターネットを通じて世界中に届けられる時代となりました。
この記事では、配信ライブを巧みに活用し、新たなファンとの関係性やビジネスモデルを構築したバンドたちの事例を7つ紹介します。
画像引用元:https://macaroniempitsu.com/
新型コロナウイルスの影響で従来の”ライブハウスに足を運ぶ”というライブ形態が難しくなった中、MTV Japanが主催となり、YouTube Liveでマカロニえんぴつの生配信イベントを実施しました。
Google Pixelとソフトバンクのサポートのもと、楽曲リクエストやX(旧:Twitter)での直接質問など、ファンがライブに参加しながらアーティストと交流できる仕掛けを導入。
リアルタイムでのファンの反応を取り入れた番組作りが、これまでにない一体感を生み出しました。
ソニーミュージックやエイベックスをはじめ、大手企業が続々とメタバースに参入。これまでに、米津玄師や星野源などの有名アーティストもメタバースを活用しています。
仮想空間上での音楽フェスやライブイベントは、物理的な会場費や工事費を大幅に削減できるメリットもありながら、世界中のファンを同時に魅了する新たな体験を提供します。
リアルとバーチャルの融合により、音楽シーンの可能性が無限に広がっています。
画像引用元:http://sokoninaru.com/bio.html
TVアニメ『魔女と野獣』OPテーマにも抜擢されている「そこに鳴る」や、ワーナーミュージック・ジャパン所属の「East Of Eden」それぞれが新曲発売を記念し、公式YouTubeチャンネルでトーク&サイン会を生配信する試みに取り組んでいます。
自宅や外出先からでも参加可能なこのオンラインイベントは、全国どこからでもファンが直接アーティストのサインを受けられる貴重な機会に。
リアルな接点を持ちながらも、デジタルならではのスピーディーなコミュニケーションが実現されています。
アメリカ出身のトップギタリスト、Andy Timmonsを迎えたオンラインセミナーは、音作りや演奏テクニックを直接学べる貴重な機会。なるべく多くの人がセミナーに参加できるよう、オフライン会場とオンライン配信を掛け合わせたセミナーが開催されました。
同セミナーは、和歌山県田辺市の会場と京都のサテライト会場を組み合わせたハイブリッド形式。現場の臨場感とオンライン配信の両方を楽しむことができるこのイベントは、教育コンテンツとしても大きな注目を集めました。
画像引用元:https://www.matenrou-opera.net/band-members
ライブハウスでの動画配信に挑戦する摩天楼オペラは、エアーマイクや複数カメラを駆使して、現場の臨場感を忠実に再現しました。
無観客ライブながら、オンライン配信ならではの工夫で海外ファンや地方在住のファンとも密にコミュニケーションを図り、音楽の魅力を余すところなく伝えました。
細やかな映像演出とスタッフの連携が、まさにプロの技そのものです。
画像引用元:https://dish-web.com/
DISH//は専用アプリ「FanStream」を活用し、ファンクラブ限定のオンラインイベントを開催。
同アプリは、コメントやギフティング機能を通じ、ファンがリアルタイムでアーティストに応援メッセージを送れる仕組みがアーティスト・ファンのどちらからも好評。
オンラインを活用することで、よりアーティストを身近に感じられる取り組みに、デジタル時代ならではのファンとの絆の深め方が光ります。
海外アーティストとのオンラインファンミーティングに特化した新サービス「Some Small Space」は、英語が苦手な日本の洋楽ファンでも安心して参加できる環境を提供。
決済システムや通訳対応で参加のハードルを下げ、国境を越えた音楽交流を実現。海外プロモーションの新たな形として、今後ますます注目されること間違いなしです。
デジタル技術の進化により、バンドとファンとの関係性はこれまで以上に多様で密接なものに変わりました。ライブ会場の制約を超えたオンラインイベント、メタバースや専用アプリの活用など、各バンドが工夫を凝らすことで、新しい音楽体験が次々と生み出されています。
これからの音楽シーンは、どのようにファンと「繋がるか」が、さらなる成功のカギとなるでしょう。