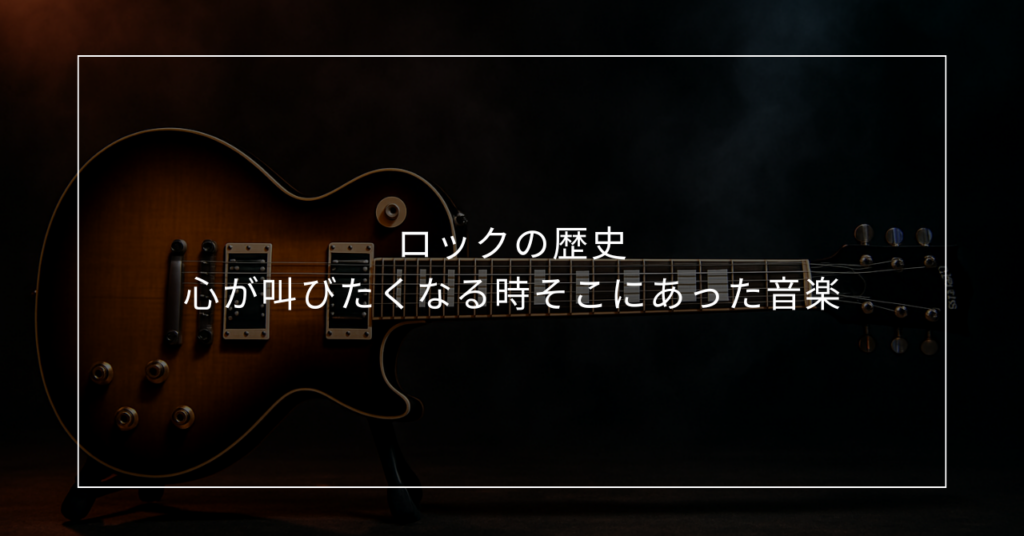あなたがもし、どこかで耳にしたギターの歪んだ音に、胸の奥がざわついた経験があるなら、あるいは、誰にも言えない本音が、歌の中にこっそりと置かれていたことがあるなら、きっと、あなたもロックに出会っているのだと思います。
今回は、そのロックがどうやって生まれ、どんなふうに姿を変えながら今の私たちに届いているのかを辿ってみましょう。
はじまりは“叫び” 〜ブルースの涙から生まれた希望の音〜
ロックの源流は、遠くアメリカ南部の労働歌やブルースにあります。
それは、生きることの痛みを歌いながらも、どこかに救いを探すような音楽でした。
やがてゴスペルやジャズ、リズム&ブルースが混ざり合い、黒人音楽のエネルギーは、白人の若者たちの心にも火をつけていきます。
そして1950年代。電気のようなギターの響きに乗せて、もっと自由に、もっと激しく、心の奥をぶつける音楽が誕生します。
それが“ロックンロール”
「チャック・ベリー」「リトル・リチャード」そして「エルヴィス・プレスリー」
彼らは踊り、叫び、時代の空気をかきまわしながら、若者たちの新しい声となっていきました。
世界を揺らした音楽 〜ロックが“思想”になった時代〜
1960年代、ロックはただの音楽ではなくなっていきます。
「ビートルズ」を筆頭に、イギリスから次々とアメリカ進出に成功し、全米チャートを席巻し、ポピュラー音楽シーンに多大な影響を与えた衝撃(ブリティッシュ・インヴェイジョン)は、世界中の若者に“自分たちにも何かができる”という勇気を与えました。
「ボブ・ディラン」はギター1本で言葉の力を見せつけ、反戦や自由、平等といったメッセージを歌に乗せました。
ロックは、世界の矛盾を暴き出す鋭い刃でもあり、同時に夢や理想を託す旗でもあったのです。
70年代になると、サウンドは重く、深くなっていきます。
「レッド・ツェッペリン」「ピンク・フロイド」「ディープ・パープル」
音の波がうねりとなり、聴く者の心を飲み込むようなスケール感を生み出していきました。ステージの上で、光と音と魂がぶつかり合いながら、ロックはまさに“時代のドラマ”そのものでした。
変わりながらも続いていく〜“今”の中に息づくロック〜
時代は変わり、80年代にはシンセサイザーの音がロックに新しい風を吹き込みます。
「U2」や「ザ・スミス」が内省的な感情を繊細に描き出し、ロックはまた違う形で人の心に寄り添うようになります。
そして90年代。音楽業界が整備され、商業化が進むなかで、「ニルヴァーナ」は短い人生の中で叫び続けました。
そのグランジの衝動は、抑え込まれた感情を一気に爆発させるように、多くの人の心を揺さぶりました。
2000年代以降、ロックは、ポップやヒップホップと融合し、ジャンルの境界線はあいまいになっていきます。
それでも「アークティック・モンキーズ」や「ザ・ストロークス」のように、新しい時代の形でロックの精神を受け継ぐバンドたちが、確かにその火をつないでいます。
あなたの中にも“ロック”は息をしている
ロックは、声にならない思いを、音にしてくれます。誰にも見せられなかった弱さを歌に乗せて抱きしめてくれる。
社会の不条理に立ち向かう力も、日常のささやかな痛みを癒す手触りも、ロックの中にはあるように感じます。
きっと今日も、どこかで誰かが自分だけのロックを鳴らしていることでしょう。
あなたの中にもそのリズムが静かに、けれども確かに響いているかもしれません。
今回は、当時の風景や、その時代の匂いすら感じられるほど、ロックへの造詣を深めていきました。それでも、音楽についてまだまだ知識の浅い筆者は、このコラムという場をお借りして知識を深めていこうと思うので、「参考になった」「面白かった」という方は、共に勉強していきましょう!
DigOut編集部のよしおでした!ではまた!